銀河バンク
"借入資本利用(レバレッジ)による、不動産貸付事業シミュレーション"
東京都心の地価と建築代の上昇が1年以上続いています。私たちは、まだまだ潜在需要が多いことから、今後も引き続き上昇が続くと考えています。
以下は、収益物件の現状(ケース1)と、上昇後(ケース2)の対応例です。
この長期シミュレーションは、私たちの短期予測を元にしたもので、状況の変化に対応できることを示したものではないことをご理解の上参考にして下さい。
◎対象とする不動産の概要
所 在 新宿・渋谷駅付近から西方向に7キロくらいまで
……若年層に人気が高く、長期安定収入が見込める地域
土 地 住居系所有権宅地25坪(防火・新防火地域含)
……投資物件としては小口で、取引も安定しているため将来は希少
建 物 木造在来準耐火構造2階建8世帯(2階ロフト付)
……安全基準が益々重要視され、低層志向も増える
想定賃料 年 576万円
月額賃料(共益費 各3,000円込)1階 57,000円 2階 63,000円
更新料・礼金、広告費は含まれていません。(取引形態変化に対応)
……単身者向け低価格物件は、2020年まで上昇が続いた後低迷。
その後は、物件不足から、年1%程度上昇すると考えています。
※備考
□借入金は、元利均等35年返済 年利 2%
……当分変わらないと思いますので、変動金利が有利と考えます。
□取得時の別途経費は、不動産取得税・印紙税、保証料、保険料、登記費用、売買仲介料、
賃貸仲介料のほか、当初空室負担等です。
……別途経費の割合は今後もこれまで通りあまり変動しないと思います。
□賃料収入に対する所得税率(必要経費控除後の額)は、20%(仮)で計算します。
……総合課税ですから、税率は事例により変わります。
但し、居住用賃料は消費税対象外です。
□不動産売却益が出た場合、取得・売却経費(売却価格の8%くらい)控除後の差益金に
不動産譲渡所得税がかかります。但し、所有期間等によって異なります。
□不動産を売却して売却損が発生した場合、他の所得と損益通算できません。
□解体整地代は、木造の場合、RCや鉄骨造のおおよそ半分です。
□所有期間の固定資産税、都市計画税は、以下、固都税等に略しました。
□維持費は、管理費(清掃含)、雑経費(共用電気・水道、ケーブル;IT対応費、印紙税等)、
メンテナンス費、補修積立金、空室リスク費で、賃料が適正であれば17%くらいです。
ケース1 想定利回り(表面)6.0%
■取得時キャッシュフロー
取得価額 9,600万円(消費税込)……土地価格 6,600万円+建物価格3,000万円
借 入 金 7,600万円
自己資金(頭金)2,000万円 ※別途経費 1,000万円
■所有期間キャッシュフロー
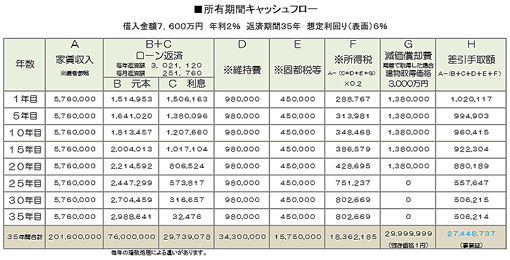
■借入返済後売却する場合のキャッシュフロー
1.更地にして、土地売りの場合
収 入 売却代金 6,600万円(土地売却益・損がない場合)
支 出 売却経費 230万円 販売手数料、印紙税、抹消登記等
原状回復費 150万円 ※解体整地代(木造)
手取額(経費控除後) 6,220万円 ※所得税はかかりません
総事業収支
2,744万円(事業益)+6,220万円(土地売却代)-3,000万円(投下資本)
=5,964万円(税引き後の純利益)
2.建物が、更に10年以上使用可能な場合 …管理が良ければ十分可能です
売却価格は、その時の利回りで決めます
……現在、中古の場合は新築より利回りを1~3%高く値付けます
売却益が出た場合(建物は簿価)は※備考参照
*その時点で、1.又は、2.の、どちらか有利な方を選択すれば良い
◎減価償却費がなくなる22年経過後、売却するという選択肢もありますが、
現在は、売却しないで事業を継続する方がほとんどです。
ケース2 想定利回り(表面)5.14%
……ケース1より建築代、土地代が1~2割程度上昇し、利回りが下がった場合
但し、税制、金利、賃貸料は変わらないとして
■取得時キャッシュフロー
取得価額 11,200万円(消費税込)、……土地価格 7,900万円+建物価格 3,300万円
借 入 金 8,200万円
自己資金(頭金)3,000万円 ※別途経費 1,100万円
■所有期間キャッシュフロー
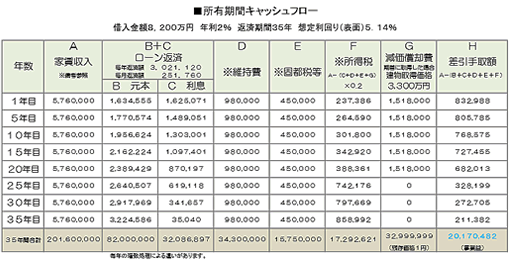
■借入返済後売却する場合のキャシュフロー
1.更地にして、土地売りの場合
収 入 売却代金 8,200万円(土地売却益・損がない場合)
支 出 売却経費 270万円 販売手数料、印紙税、抹消登記等
原状回復費 150万円 ※解体整地代(木造)
手取額(経費控除後) 7,780万円
総事業収支
2,017万円(事業益)+7,780万円(土地売却代)-4,100万円(投下資本)
=5,697万円(税引き後の純利益)
売却益が出た場合(建物は簿価)は※備考参照
2.ケース1と同じ
*その時点で、1.又は、2.の、どちらか有利な方を選択すれば良い
◎減価償却費がなくなる22年経過後、売却するという選択肢もありますが、
現在は、売却しないで事業を継続する方がほとんどです。





